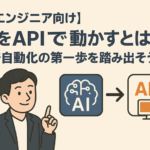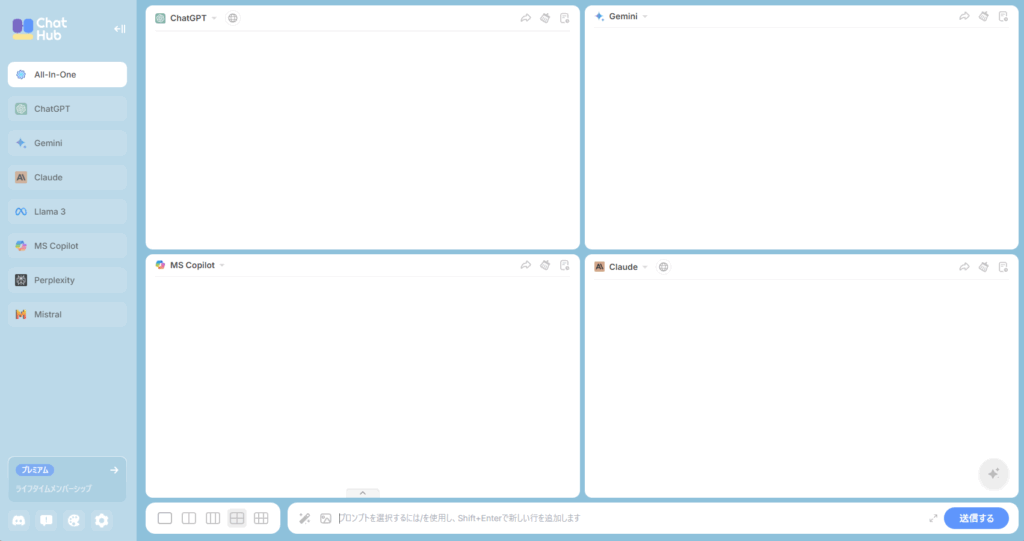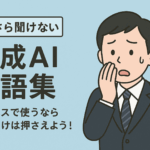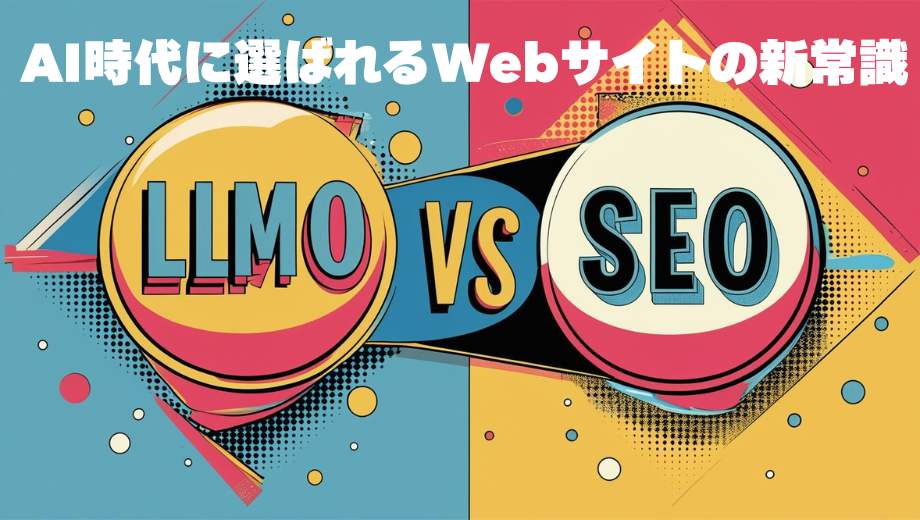
「最近、Webマーケティング界隈で『LLMO』という言葉を耳にするようになったけど、一体何のことだろう?」
「これまで頑張ってきたSEO対策だけでは、もう時代遅れになってしまうのだろうか?」
中小企業の経営者様やWebご担当者様の中には、こうした新しい言葉の登場に、期待と同時に一抹の不安を感じていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。
ご安心ください。
この記事を読めば、LLMOとSEOの違いから、これからの時代にAIから選ばれるWebサイトになるための具体的な方法まで、スッキリと理解できます。
まずはおさらい!これまでの常識「SEO」とは?
本題に入る前に、まずは多くの方がご存知の「SEO」について簡単におさらいしましょう。
SEOとは「Search Engine Optimization」の略で、日本語では「検索エンジン最適化」と訳されます。
ものすごく平たく言うと、「GoogleやYahoo!などの検索エンジンで、自社のWebサイトを上位に表示させるための様々な工夫」のことです。
例えば、お客様が「東京駅 おすすめ ランチ」と検索した時に、自社のレストランの紹介ページが1ページ目の、それもなるべく上の方に表示されれば、クリックしてもらえる可能性が高まりますよね。
その結果、お店の存在を知ってもらい、来店に繋がるかもしれません。
この「検索結果の上位表示」を目指す活動がSEO対策です。
キーワード選定、コンテンツ作成、内部対策、外部対策などがあります。
これまで多くの企業が、このSEO対策に時間と労力を費やし、自社サイトへの集客を目指してきました。
これは今でもWebマーケティングの重要な柱の一つです。
AI時代の新常識「LLMO」とは?
さて、いよいよ本日の主役「LLMO(エルエルエムオー)」の登場です。
LLMOとは「Large Language Model Optimization」の略。日本語にすると「大規模言語モデル最適化」となります。
…と言われても、ピンと来ないですよね。大丈夫です、順番にご説明します。
まず、「大規模言語モデル(LLM)」とは、ChatGPTなどに代表される、膨大なテキストデータを学習して、人間のように自然な文章を生成したり、質問に答えたりできるAIのことです。
非常に賢く、博識なアシスタントをイメージしてください。
そして「LLMO」とは、この賢いAIアシスタントに、こちらの聞きたいこと(情報)をうまく伝えて、最適な回答を引き出すための工夫…ではなく、Webサイト運営側の文脈では、AIが回答を生成する際に、自社のWebサイトの情報を“情報源”として引用・参照してもらうための最適化を指します。
つまり、SEOが「検索エンジン」を対象とした最適化であるのに対し、LLMOは「生成AI(大規模言語モデル)」を対象とした最適化なのです。
なぜ今、LLMOが重要なのか?
「でも、AIに引用されることって、そんなに大事なの?」と思われるかもしれません。
非常に大事です。
その理由は、検索の仕方が変わり始めているからです。
代表的な例が、Googleが導入を進めている「SGE(Search Generative Experience)」です。
これは、検索結果の最上部に、AIが生成した要約を表示する新しい検索体験です。
(画像:SGEでは、従来の検索結果の上にAIによる要約が表示される)
例えば、先ほどの「東京駅 おすすめ ランチ」で検索すると、SGEは様々なWebサイトの情報を基に、「ビジネス向けなら個室のあるA店、子連れならキッズメニューが豊富なB店、コスパ重視ならC店のランチセットがおすすめです」といった要約を自動で作成して提示します。
そして、その情報の引用元として、A店、B店、C店のWebサイトへのリンクが表示されるのです。
ユーザーは、いちいち複数のサイトを巡回しなくても、このAIの要約を読むだけで、ある程度の答えを得られます。これを「ゼロクリック検索」と呼びます。
この流れが進むと、AIの要約に引用されるかどうかが、自社の情報をユーザーに届けるための、極めて重要な“入口”になることは、容易に想像がつくでしょう。
だからこそ今、LLMOが注目されているのです。
【徹底比較】LLMOとSEO、何がどう違うの?
ここで、LLMOとSEOの違いを分かりやすく表にまとめてみましょう。
| 項目 | SEO(検索エンジン最適化) | LLMO(大規模言語モデル最適化) |
| 目的 | 検索結果で上位に表示させ、サイトへのクリック(流入)を増やす | AIの生成する回答に引用・参照され、情報源としての信頼性を高める |
| 対象 | Googleなどの検索エンジン(アルゴリズム) | ChatGPTなどの生成AI(大規模言語モデル) |
| 評価されるもの | キーワードとの関連性、検索意図の理解、サイトの使いやすさ など | 情報の正確性、信頼性、専門性、文章の分かりやすさ、情報の独自性 |
| 主な対策 | キーワード調査、コンテンツ作成、技術的SEO(サイト高速化など) | E-E-A-Tの強化、構造化データ、一次情報の発信、分かりやすい文章構造 |
| 最終的なゴール | 自社サイトへの送客 | AIによる“お墨付き”の獲得、ブランド認知の向上 |
Google スプレッドシートにエクスポート
一番の大きな違いは、そのゴールです。
- SEOは、検索順位というランキングを上げて、ユーザーを自社サイトに呼び込むのが主目的です。
- LLMOは、AIという賢いアシスタントに「この情報源は信頼できますよ」と認めてもらい、その回答の一部として紹介してもらうことが主目的です。
「じゃあ、もうSEOはやらなくていいの?」
「LLMOが大事なのは分かった。じゃあ、これからはSEO対策をやめて、LLMO対策に全振りすればいいの?」
いいえ、それは早計です。結論から言うと、LLMOとSEOは対立するものではなく、両輪で進めるべきものです。
実は、LLMOで評価されるための要素の多くは、質の高いSEO対策と共通しています。
例えば、ユーザーの疑問に的確に答え、専門的で信頼できるコンテンツを作ることは、SEOでもLLMOでも同様に重要です。
むしろ、これまで真面目にSEOに取り組んできたWebサイトは、LLMOにおいても非常に有利なポジションにいると言えます。
SEOで築き上げた土台が、そのままLLMO対策の強固な基礎となるのです。
明日からできる!LLMOでAIに選ばれるための5つの秘訣
それでは、具体的に何をすれば、AIから「このサイトの情報は信頼できる!」と選んでもらえるようになるのでしょうか。
ここでは、専門知識がない方でも今日から意識できる5つの秘訣をご紹介します。
秘訣1:「誰が言っているか」をとことん明確にする(E-E-A-Tの強化)
AIは、その情報が「誰によって」発信されたのかを非常に重視します。そこで重要になるのが「E-E-A-T」という考え方です。
- E (Experience - 経験): 実際に体験したことに基づいているか?
- E (Expertise - 専門性): その分野の専門家が書いているか?
- A (Authoritativeness - 権威性): その分野で広く認められているか?
- T (Trust - 信頼): 情報は正確で信頼できるか?
これらは、もともとGoogleがSEOで良いコンテンツを評価するための基準ですが、LLMOではさらにその重要度が増します。
- 著者情報を明記する: 記事の末尾に、執筆者の顔写真、名前、役職、経歴、保有資格などを具体的に記載しましょう。
- 監修者を入れる: 専門的な内容であれば、その道の専門家に監修を依頼し、その旨を明記します。
- 「会社概要」ページを充実させる: 会社の沿革、事業内容、代表者の想い、所在地などを詳しく記載し、「私たちは何者で、どんな想いでこの事業を行っているのか」を明確に伝えましょう。
秘訣2:AIにも分かる「丁寧語」で話す(分かりやすい文章構造)
AIは非常に賢いですが、人間のように「行間を読む」のはまだ少し苦手です。そのため、AIが内容を誤解なく正確に理解できるよう、分かりやすい文章構造を心がけることが大切です。
- 結論ファースト: まず結論を述べ、その後に理由や具体例を説明する構成にしましょう。
- 見出しを適切に使う:
<h1>、<h2>、<h3>といった見出しタグを使い、文章の階層構造を明確にします。 - 箇条書きや表を活用する: 情報を整理して、視覚的に分かりやすく伝えましょう。
- 一文は短く、簡潔に: 専門用語や難しい言い回しは避け、誰が読んでも理解できる平易な言葉で書きましょう。専門用語を使う際は、必ず注釈を入れます。(例:LLMO(大規模言語モデル最適化)とは〜)
秘訣3:一つのことを、とことん深掘りする(網羅性と独自性)
他のサイトにも書いてあるような一般的な情報だけでは、AIから「情報源」として選ばれることはありません。あなたの会社だからこそ語れる、独自の視点や一次情報が不可欠です。
- お客様の声を載せる: 導入事例やお客様のインタビューは、最高の一次情報です。
- 独自の調査データを公開する: 社内で実施したアンケート結果や、業界に関する独自の分析などをコンテンツに盛り込みましょう。
- 失敗談も語る: 成功体験だけでなく、「こんな失敗からこんなことを学んだ」というストーリーは、非常に価値のある独自コンテンツになります。
- FAQ(よくある質問)コーナーを作る: お客様からよく寄せられる質問とその回答をまとめたページは、ユーザーにとってもAIにとっても非常に有益な情報源となります。
秘訣4:情報に「名札」をつける(構造化データの活用)
これは少しだけ技術的な話になりますが、非常に効果的です。構造化データとは、Webページ上の情報が「これは会社の住所です」「これは商品の価格です」「これはイベントの開催日時です」といったように、何を表す情報なのかを検索エンジンやAIに伝えるための“名札”のようなものです。
名札がついていれば、AIは情報を正確に認識し、回答に利用しやすくなります。
- WordPressのプラグインを活用する: WordPressをお使いの場合、「All in One SEO Pack」や「Yoast SEO」といった有名なSEOプラグインには、基本的な構造化データを簡単に追加できる機能が備わっています。まずはFAQ(よくある質問)の構造化データなどから試してみるのがおすすめです。
- Web制作会社に相談する: 自社での対応が難しい場合は、Webサイトを制作・管理してくれているパートナー会社に「LLMO対策として、構造化データに対応したい」と相談してみましょう。
秘訣5:正直で、誠実であること(情報の正確性と鮮度)
最後の秘訣であり、最も重要なことです。AIは、Web上の膨大な情報を比較・検証し、矛盾や不正確な情報を見抜く能力に長けています。
小手先のテクニックでごまかそうとせず、常に正確で、最新の、そしてユーザーのためになる誠実な情報発信を心がけること。これが、結果的にAIからの信頼を勝ち取る一番の近道です。
- 情報の出典を明記する: 統計データなどを引用する場合は、必ず官公庁や信頼できる調査機関などの出典元を明記しましょう。
- コンテンツを定期的に見直す: 一度公開した記事も、情報が古くなっていないか定期的にチェックし、必要であれば更新しましょう。「最終更新日」を明記することも信頼性向上に繋がります。
まとめ:AIと共に成長するWebサイトへ
今回は、AI時代の新たなWebサイトの考え方である「LLMO」について、SEOとの違いや具体的な対策を解説しました。
最後に、重要なポイントをもう一度おさらいします。
- SEOは「検索エンジン」で上位表示を目指す活動。
- LLMOは「生成AI」の回答に引用されることを目指す活動。
- これからはSEOとLLMO、両輪で考えることが重要。
- LLMO対策の鍵は「信頼性・専門性・独自性」であり、小手先のテクニックではなく、ユーザーに対する誠実な姿勢が何よりも大切。
新しい言葉や技術が登場すると、つい難しく考えて身構えてしまいがちです。しかし、LLMOの本質は非常にシンプル。それは「あなたの会社や商品、サービスのことを、もっと深く、正しく、正直に伝えましょう」ということです。
AIは、決して私たちの仕事を奪う脅威ではありません。私たちの発信する“価値”を、それを必要としている人々に、より的確に届けてくれる頼もしいパートナーです。
ぜひ、本日の内容を参考に、AIを味方につけ、ビジネスをさらに加速させる一歩を踏み出してみてください。
「生成AI活用塾」は、これからも中小企業の皆様の「知りたい」「やってみたい」を応援する情報を発信していきます。